2025年4月4日
京都市下京区の「鈴木内科医院」の
オーダーメイド生活習慣病治療で
健康寿命の延伸をサポート

高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病は、放置すると重篤な合併症を引き起こす可能性があります。鈴木内科医院では、患者さまお一人ひとりの生活環境や職業、嗜好を考慮したオーダーメイドの生活習慣病治療を実践。無理のない範囲での生活改善と、必要に応じた適切な薬物療法を組み合わせることで、長期的な健康維持をサポートします。健診で数値の異常を指摘された方や、生活習慣病について不安のある方は、早めのご相談をおすすめします。
院長よりメッセージ


院長鈴木 隆裕
Suzuki Takahiro
京都市下京区仏光寺油小路にある鈴木内科医院は、父の代から二代にわたって地域医療に携わってきた内科クリニックです。長年の診療実績を通じて培われた地域との信頼関係を基盤に、現代の生活習慣病に対応する先進的な医療サービスをご提供しています。特定健診をはじめとする各種健康診断にも対応し、生活習慣病の早期発見に努めるとともに、患者さまお一人ひとりの生活環境に合わせたオーダーメイドの生活指導と治療を実践。世代を超えて通院される患者さまが多く、長期的な健康管理と生活習慣病予防に力を入れています。
featuresfeatures医療ライターから見た
鈴木内科医院の
生活習慣病治療の特徴

オーダーメイドの生活習慣指導で実現する継続可能な治療
鈴木内科医院の生活習慣病診療の最大の特徴は、画一的な指導ではなく、患者さまお一人ひとりの生活環境や職業、家庭環境を考慮したオーダーメイドの生活習慣指導にあります。「できること」と「できないこと」を患者さまと共に見極め、無理なく継続できる改善策を提案するアプローチは、長期にわたる治療の成功率を高める重要な要素です。特に働き盛りの世代の継続診療を意識した配慮が随所に見られ、小さな成功体験を積み重ねることで患者さまのモチベーションを維持する工夫がなされています。
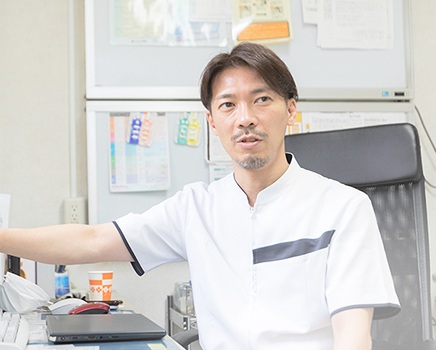
多職種連携による総合的な
生活習慣病管理
生活習慣病は食事、運動、睡眠など多岐にわたる要因が絡む複雑な疾患群です。特に注目すべきは、睡眠時無呼吸症候群と高血圧の関連に着目し、若年性の高血圧患者に対する睡眠時無呼吸症候群のスクリーニングを積極的におこなっている点です。
このような多角的なアプローチにより、生活習慣病の根本的な原因に迫る総合的な疾患管理を実現しています。

地域のかかりつけ医として
の長期的な健康管理
何世代にもわたって診療を続けるご家族も多い鈴木内科医院では、地域のかかりつけ医として患者さまの長期的な健康管理に力を入れています。また、薬の管理においても、高齢患者さんの多剤服用の負担を軽減するため、合剤の活用や定期的な処方見直しをおこなうなど、きめ細かな配慮が見られます。こうした長期的な視点での健康管理により、生活習慣病の重篤な合併症を予防し、患者さんのQOL(生活の質)向上に貢献しています。
interviewinterview院長 「鈴木 隆裕
(すずき たかひろ)」先生
に独自取材

生活習慣病の診療において、特に大切にされている点は何ですか?
生活習慣病はその名の通り、生活習慣から来るものです。同じ病気でも患者さんによって生活スタイルや食べ物の嗜好、仕事もさまざまです。また、お仕事や家庭環境などによって、「できること」と「できないこと」があります。無理な指導で仕事や生活に支障をきたしたり、大きなストレスとなっては逆効果です。

- 患者さんの生活習慣や生活スタイルをよく聞きながら、その方に合うようにお薬はもちろん、指導も行うようにしています。
- 無理のない範囲での生活習慣の改善をできるだけ継続できるよう、患者様と一緒になってサポートします。
- 一人ひとりの状態に応じた最適な治療方針を立て、長期的な健康維持をサポートします。
生活習慣病の診療に対する先生の基本的な考え方を教えてください。
当院では生活習慣病の診断・治療に力を入れています。
健康診断で数値の異常を指摘された方は、早めのご相談をおすすめします。
治療の基本は生活習慣の改善ですが、画一的な指導ではなく、
患者さん一人ひとりの生活環境に配慮したオーダーメイドの指導を心がけています。
どんなに効果的な治療法でも、続けられなければ意味がありません。患者さんが無理なく継続できる方法を一緒に見つけていくことが、生活習慣病治療のカギだと考えています。そして、生活習慣の改善だけでは効果が不十分な場合は、適切な薬物療法も組み合わせて対応します。
働き盛りの患者さんが治療を続けるためにどのような工夫をしていますか?
モチベーションを持ってもらうことが大切ですね。治療に取り組む姿勢や努力しているところをなるべく見つけて褒めてあげるようにしています。
少しでも病院に来やすいように心がけています。
どのように患者さんのモチベーションを上げておられるのですか?
ちょっとでもダイエットに成功したり、良い変化があれば必ず伝えるようにしていますね。継続のためには、そういった小さな成功体験の積み重ねが大切だと思います。また、働き盛りの方は時間の制約も多いので、診察時間の調整や、効率的な治療計画の提案などもおこなっています。
生活習慣病の治療で薬を使うタイミングはどう判断されますか?
最初は生活習慣の見直しから始めます。患者さんと一緒に「これくらいなら週に1回歩けるかな」というように、運動や食事の改善を考えていきます。
私もそうなのですが、頑張ってもなかなか結果に結びつかないことがありますよね
そうすると患者さんも医師自身も両方フラストレーションが溜まりますから、ある程度努力をしてみた上で、それでも結果が出ないときには薬を使うことを提案します。ただし、数値の悪化が著しい場合や、既に合併症のリスクが高い状態の場合は、早期から薬物療法を併用することもあります。
「一生薬を飲み続けなければならない」と抵抗を感じる患者さんにはどう対応されますか?
特に中高年の方に多いですね。そういう方には「一緒に頑張りましょう」という形で、私自身も運動していることを伝えます。例えば「私は週末にこれくらい歩いているのですが、どれくらいなら歩けそうですか?」などと話しながら、運動を促したりしています。私も週末は往復9キロほど歩いています。走りたいのですが膝が良くなくて走ると痛くなるので、歩くことを選んでいます。このように具体例を挙げながら一緒に頑張る姿勢を見せることが大切だと考えています。
食事指導についてはどのようなアプローチをされていますか?
食事や運動はみんなできれば改善したいと思っていても、
食事制限はしたくないという気持ちが強いものです。
ですから、厳しく言うべき人にはもちろん言いますが、基本的にはあまり厳しく言わないようにしています。それよりは運動の方をすすめることが多いですね。ただ、糖尿病の方など、どうしても食事制限が必要な場合は、患者さんと相談しながら何か楽しみになるものは残してあげるようにしています。すべてを奪い取ってしまうと、長続きしないですからね。
塩分の多い京都の食文化、減塩にはどのようなアドバイスをされていますか?


京都の食べ物は意外と塩気が多いですね。
特にお年寄りはお漬物やお茶漬けが好きな方が多いです。
「塩はかけていません」と言っても、お漬物などに結構塩分が含まれていることが多いです。毎日漬物や梅干しを食べているとわかったら「ちょっと多いね」という話から始めて、「1日おきにしませんか?」などと提案します。
一切やめてくださいとは言いません。
無理のない範囲で減らしていただくようにしています。
患者さんご自身が「多いのですか?」と気付くことが大切ですね。
栄養指導などはどのようにおこなわれていますか?
栄養指導は非常に重要ですが、一般の開業医としてできることには限界があります。そのため、必要に応じて病院の栄養士さんと連携して、より専門的な栄養指導を受けていただくこともあります。栄養士さんは男性の方には仕事や外食の状況を考慮したアドバイスをしてくださいますし、女性の方には家庭での調理法なども含めた具体的なアドバイスをしてくださいます。
睡眠時無呼吸症候群と生活習慣病の関連についてはいかがでしょうか?
睡眠時無呼吸症候群は特に高血圧との関連が強いと言われています。若いのに血圧が高かったり、通常の体型なのに血圧が高かったりする方には、睡眠時無呼吸症候群が隠れていることがあります。それを治療することで血圧が落ち着くこともあります。
逆に、睡眠時無呼吸症候群がある人は将来的に血圧が高くなり、心不全のリスクも高まります。いびきがひどかったり、寝ている間に呼吸が止まったりしていると指摘される方は一度検査をおすすめします。
検査は痛くないのですか?
簡易検査があります。自宅で時計のようなバンドの装置を装着して寝るだけで診断ができますし、保険適用です。若い方でも睡眠時無呼吸症候群が原因で高血圧になっているケースは少なくありませんのでぜひおすすめしたいです。
複数の疾患を抱える高齢者の薬の管理についてはどうされていますか?
高齢の患者さんでは、高血圧、糖尿病、脂質異常症など複数の生活習慣病を抱えていることが少なくありません。そうなると薬の数も増え、管理が大変になります。
当院では、なるべく薬の数を減らせるよう、合剤(複数の薬を一つにまとめたもの)を活用したり、本当に必要な薬かを定期的に見直したりしています。
薬を継続して飲むのは大変なことですから、飲みやすいように工夫していますし、飲み忘れ防止のカレンダーの活用なども提案しています。患者さんの生活リズムに合わせた服薬スケジュールを考えることも重要です。

健康診断の結果をどのように活用していますか?
健康診断は生活習慣病の早期発見・早期治療のためのとても重要な機会です。
当院では特定健診なども実施していますが、健診で異常値が出た場合は、なるべく早く受診していただくようおすすめしています。健診結果を過去のデータと比較しながら分析し、生活習慣の何が影響しているのかを一緒に考えていきます。
健康診断で「異常なし」は安心して良いのですか?
健診では「異常なし」と判定されても、境界域の数値があれば将来のリスクとして注意を促すこともあります。健診は受けるだけでなく、その結果を理解して今後の生活習慣改善や治療に活かすことが大切ですね。
長年患者さんを診てこられて、成功する治療に特徴はありますか?

長年診療していて感じるのは、まずは患者さん自身が自分の状態をしっかり理解し、治療の必要性を納得することが大切だということです。
検査結果の説明や病気のメカニズムなどをわかりやすく伝えるよう心がけています。
無理のない目標設定も大切ですね。いきなり大きな変化を求めるのではなく、小さな成功体験を重ねていくことで自信につながり、継続的な改善が可能になります。
そして何より、医師と患者さんの信頼関係が基盤にあることが成功のカギだと思います。当院には何世代にもわたって通ってくださるご家族もいらっしゃいますが、そういった長期的な関係の中で共に健康を守っていくことを大切にしています。



