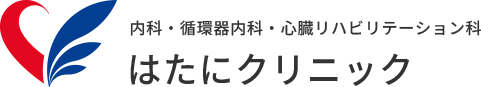2025年5月12日
“なんとなく不安”から始まる
循環器疾患のサインを見逃さない
神戸市須磨区の「はたにクリニック」



はたにクリニックは、「治療の主は患者さま」という思いのもと、年齢や生活背景に合わせた個別化医療を実践し、症状や状態に応じて大病院とも連携しながら、地域の循環器医療の拠点としての役割を担っています。また、須磨区、長田区、垂水区では数少ない慢性期の心臓リハビリテーションを提供するクリニックとして、心臓疾患後の患者さまも積極的に受け入れています。
院長よりメッセージ


院長羽溪 優
Hatani Yutaka
日本循環器学会認定循環器専門医かつ日本超音波医学会超音波専門医という専門医資格を持ち、神戸大学医学部附属病院や神戸労災病院などでの経験を活かした質の高い診療をご提供しています。心不全、不整脈、弁膜症、高血圧などの循環器疾患に加え、生活習慣病にも対応し、地域の皆様の健康維持をサポートしています。
featuresfeatures医療ライターから見た
はたにクリニックの
循環器疾患の特徴

専門性と経験を活かした
精度の高い診断
何か変な違和感という微細な変化にも気づく目は、単なる知識だけでなく、多くの症例経験に裏打ちされたものです。「自分で端から端まで映し出して、自分が納得する所見を出さないと」という責任感を持った診療姿勢も、はたにクリニックの大きな特徴と言えます。

予防医学と早期発見を重視した
総合的アプローチ
はたにクリニックでは「早期発見・早期治療」という循環器診療の基本原則を大切にしています。循環器っていうのは命に関わる病気につながるという危機感をいつも持ち、早期の段階で適切な対応を行うことで、重篤な状態への進行を防ぐことに尽力しています。

地域に根差した継続的かつ
専門的な医療の提供
はたにクリニックは須磨区、長田区、垂水区では数少ない慢性期の心臓リハビリテーションを提供するクリニックとして、地域医療において重要な役割を果たしています。大病院での循環器疾患診療の経験を活かし、地域の循環器医療を担っています。
interviewinterview院長羽渓優
(はたにゆたか)
先生に
独自取材

循環器疾患にはどのような種類がありますか?代表的な症状を教えてください。
循環器疾患の代表的なもの
- 心筋梗塞
- 狭心症
- 心不全
- 弁膜症
- 不整脈
- 大動脈解離
などが挙げられます。これらは「動脈硬化性疾患」と総称されることもあり、脳梗塞なども含めて命に関わる重大な疾患です。
代表的な症状とは?
- 坂道や階段を上った時に胸が痛くなったり息切れがする(これは狭心症の可能性を示唆しています)
- 足のむくみが取れない、あるいはむくみがだんだんひどくなる(心不全の疑い)
- 夜間、横になって寝たときに咳が出る(心不全の症状)
- 座っていても息苦しい(より進行した心不全の症状)
これらの症状が持続する場合は、早めに循環器専門医に相談することをおすすめします。
「何もなかった」と分かれば安心ですし、問題があれば早期に対応できます。
「病気って外れくじを引けばいい」という考え方で、早めに受診することが大切です。
症状はなくても、健康診断で循環器系の異常(高血圧、心電図異常、脂質異常症など)を指摘された場合は?
「要経過観察」と言われても放置せず、専門医に相談することが大切です。
下手に不安がらなくてもいいので、一度確認しにお越しいただければ良いかと考えています。
病気でなかったとわかったら「何でもなかった、ハハハ」で笑える状態であれば問題ありませんよね。
心臓の超音波検査(エコー)では何がわかりますか?専門医による違いは?
心臓の超音波検査(エコー)では、心臓の構造や機能を非侵襲的に評価することができます。心臓の大きさや壁の厚さ、弁の状態、心臓の収縮力、血液の流れなどを詳細に観察できるため、心不全、弁膜症、心筋梗塞の後遺症など、心臓疾患の診断に役立ちます。

専門医による検査は違いがあるのですか?
専門医による違いは非常に大きいです。これは「見る人というか、取る技量の問題」だからです。「心臓を端から端まで取る」というトレーニングを受けた医師とそうでない医師では、得られる情報量が大きく異なります。どのように画像を取得するかの手技が極めて重要です。
また「どれだけの病気を念頭に置いているか」という知識や経験も重要です。「数をたくさん見ている」医師は「何か変な違和感」という微細な変化にも気づくことができます。
「端から端まで映し出して、自分が納得できるまで画面と向き合う」という姿勢で検査を行っています。
「狭心症」と「心筋梗塞」の違いを教えてください。
狭心症と心筋梗塞はどちらも冠動脈(心臓の筋肉に血液を送る血管)に問題が生じる疾患ですが、重症度と状態が異なります。
狭心症は冠動脈が一時的に狭くなって心臓の筋肉(心筋)に十分な血液が流れなくなる状態です。典型的な症状としては「坂道や階段を上った時の胸痛や息切れ」といった労作時の胸痛や圧迫感があります。安静にすると症状は治まりますが、これは心筋梗塞の「予兆」となることもあるのでしっかり検査が必要です。
一方、心筋梗塞は冠動脈が完全に詰まり、心筋の一部が壊死する重篤な状態です。胸の激痛、冷や汗、吐き気などの強い症状が現れ、命に関わる緊急事態です。
近年はいい薬剤もできていますので、重篤な心筋梗塞の発症率が低下して印象があります。
予防と早期発見のためには、症状が持続している場合には、放っておかないことが大切です。
心不全とはどのような状態ですか?
心不全は「心臓がポンプとしての機能を十分に果たせなくなった状態」を指します。これは特定の病気の名前ではなく、総称です。複数の原因から心臓の機能が低下した状態を指します。
主な原因としては、「心臓弁膜症による心不全」「不整脈による心不全」などさまざまな要因があります。基本的には心臓に何かの原因があって、ポンプ機能が失われている、損なわれている状態です。この原因によって治療方針も変わってきます。
心不全の主な症状と対処法を教えてください。
典型的な症状としては「足のむくみが取れない」「顔がむくんでくる」などのむくみ(浮腫)、「夜間、横になって寝たときに咳が出る」などの夜間呼吸困難、全体的な息切れや疲労感などがあります。進行すると「座っていても息苦しい」状態になることもあります。
基本的な対処法としては、
- 減塩と適度な運動
- バランスの良い食事
- 内服をきちんとする
特に「減塩」は心不全管理の基本で、むくみがある方は塩分制限が必要です。
また今はいい薬があるのでので、適切な薬物療法により症状のコントロールが可能です。
循環器疾患の予防に重要な生活習慣について教えてください。
循環器疾患の予防に重要な生活習慣の基本は、食事と運動です。
食事面では、塩分制限が特に重要です。栄養バランスについては、三大栄養素のことは常日頃から皆さまにお伝えしています。
- タンパク質はしっかりと
- 脂質は極力抑えるつもりで
- 炭水化物は体重の減り具合でちょっと食べかたを変える
運動については、特に心臓リハビリテーションのデータからも週3回程度の適切な頻度と強度の運動が効果的です。
「活動性が上がる」ことで全身の健康状態が改善します。

他に気をつけることはありますか?
禁煙、適度な飲酒、十分な睡眠、ストレス管理なども重要です。また「早期発見早期治療」のために定期的な健康診断を受けることも予防には欠かせません。
年齢に関わらず、何か症状が出始めて持続するのであれば専門医に相談することが大切です。
循環器疾患の検査にはどのようなものがありますか?それぞれの特徴を教えてください。
循環器疾患の検査には、症状に応じて最適な検査を選択します。症状をしっかりと確認し、お一人ひとりに合わせた検査プランを立てることが重要です。
心臓超音波検査(エコー)
非侵襲的に心臓の構造や機能をくわしく観察できる検査で、超音波専門医による検査では「端から端まで」心臓を詳細に評価することができます。弁膜症や心不全、心筋梗塞後の状態などの評価に非常に有用です。
24時間の心電図
動悸や不整脈の症状がある場合に用いられます。これは日常生活中の心電図を24時間記録し、発作的な不整脈などを捉えることができます。
運動負荷心電図
「労作時の胸痛」などの症状がある場合におこないます。
頚動脈エコー
動脈硬化の状態を評価します。
必要に応じて血液検査、胸部X線検査なども行います。
重症な場合と判断されたときは?
重篤な場合や詳細な評価が必要な場合は「大病院へ」紹介し、冠動脈CT、心臓MRI、心臓カテーテル検査などの精密検査を行うこともあります。
重要なのは、困った症状に対して検査を行うことで、ピンポイントで必要な検査を専門医の経験で選択します。
たくさんの症例を見てきた経験が活かされています。
高血圧が循環器疾患に与える影響について教えてください。
高血圧は循環器疾患の主要なリスク因子です。血圧が高い状態が継続すると、全身の血管に大きな負担がかかり、動脈硬化を促進します。心筋梗塞や脳梗塞など命にかかわる動脈硬化性疾患を引き起こすリスクが高くなります。
高血圧は、
- 心臓の筋肉(心筋)が厚くなる「心肥大」を引き起こし、長期間続くと心臓の機能が低下し、心不全のリスクが高まります。
- 大動脈瘤や大動脈解離といった致命的な疾患のリスクも増加させます。

高血圧はどのように治療されるのですか?
高血圧の管理には生活習慣の改善と薬物療法を併用することで、最も効果的に高血圧を管理し、循環器疾患のリスクを低減することができます。
ただし、「好きなものを食べてお薬を飲んで治療というのは意味がないという認識も大切ですね。
弁膜症とはどのような病気ですか?主な種類と症状を教えてください。
弁膜症は心臓の弁に異常が生じる疾患の総称です。心臓には4つの弁(僧帽弁、三尖弁、大動脈弁、肺動脈弁)があり、これらが血液の逆流を防いで一方向に流れるよう調節しています。弁膜症ではこの弁の開閉に問題が生じ、血液の流れが妨げられる「狭窄症」や逆流してしまう「閉鎖不全症」が起こります。
軽度の場合は無症状のことも多いですが、進行すると「息切れ」「動悸」「疲労感」「むくみ」などが現れます。
弁膜症ってどのような検査をするのですか?
弁膜症の診断には、超音波検査(エコー)が非常に重要で、「超音波専門医による検査」が高い診断精度につながります。
超音波専門医なので超音波専門医読影力は高いという強みが活かされます。
不整脈にはどのような種類がありますか?治療法について教えてください。
不整脈は心臓の電気的な活動に異常が生じて心拍のリズムが乱れる状態のことです。
- 脈が遅くなる「徐脈性不整脈」(洞不全症候群、房室ブロックなど)
- 脈が速くなる「頻脈性不整脈」(心房細動、発作性上室性頻拍、心室頻拍など)があります。
症状
- 動悸
- めまい
- 失神
- 胸部不快感
- 無症状の場合もあります
特に「動悸で来られる方」は24時間心電図検査などでくわしく調べる必要があります。
軽度の不整脈では経過観察のみでよい場合もありますが、症状が強い場合や命に関わるリスクがある場合は積極的な治療が必要です。薬物療法は多くの不整脈で第一選択として用いられ、良いお薬もあるので、症状のコントロールが以前より良好になっています。
動脈硬化が引き起こす病気にはどのようなものがありますか?
- 脳梗塞
- 心筋梗塞
- 大動脈解離
ありとあらゆる疾患のリスクが高まります。
心臓では冠動脈が硬化・狭窄することで「狭心症」や「心筋梗塞」を引き起こします。
脳では頚動脈や脳動脈の硬化により「脳梗塞」が起こります。脳の血管が詰まることで脳組織に損傷が生じ、後遺症が残る可能性があります。また、動脈硬化に伴う高血圧により「脳出血」のリスクも高まります。大動脈では「大動脈瘤」や「大動脈解離」といった致命的な疾患を引き起こすことがあります。大動脈の壁が弱くなり膨らんだり(瘤)、裂けたり(解離)する状態です。
下肢では「末梢動脈疾患」を引き起こし、歩行時の痛みや、重症では壊疽につながる可能性もあります。また腎動脈の硬化は「腎機能障害」や「腎不全」の原因となり、最終的には「透析」が必要になることもあります。
若年者でも循環器疾患のリスクはあるのでしょうか?
若年者でも循環器疾患のリスクは確実にあります。最近やっぱり35歳前後の方が来られるケースも増えています。
若年者の循環器疾患リスクとして、特に注意すべきは生活習慣病です。
高血圧、脂質異常症、糖尿病などは若い年齢でも発症することがあり、これらは将来的な心筋梗塞や脳卒中などの重大な循環器疾患のリスク因子となります。若い方は治療の効果の反応がいいという利点がある一方で、自覚症状がないまま危険因子が蓄積していくこともあります。
若年者の大きな特徴として「ご飯の作り方を知らない」ことが挙げられます。
「こういう味付けとか、忙しいからこういう作り置きをした方がいい」などの栄養士から具体的なアドバイスが必要な場合も多いです。特に「子供産んで太りやすい」若い女性に対しては「もったいない精神を捨てなさい」「子どもの残りを食べないで」といった実践的なアドバイスも行なっています。
年齢とともに気をつけるべき循環器疾患のリスクについて教えてください。
年齢によって気をつけるべき循環器疾患のリスクは変わります。
若年層では、生活習慣病のリスク因子に注意が必要です。
中高年になると、動脈硬化性疾患のリスクが高まります。頚動脈エコーをして、プラークが多い場合は早期の介入が必要です。
高齢者、特に80〜90代後半になってきたら、あとはご本人とご家族との理解が重要です。
余生をいかに気持ちよく楽しく過ごしていただくかを優先し、無理な治療よりも生活の質を重視することも大切です。また、慣れ親しんだ生活を変えることに抵抗のある方も多いため、薬物療法を積極的に取り入れることが多くなります。食べて元気な方を優先する考え方で、高齢者にあれも食べるな、これも食べるなっていうと、やっぱり痩せてきてしまい動けなくなるリスクがありますからね。
若年層ほど予防的・長期的な視点で、高齢者ほど生活の質を重視したアプローチが望ましいですね。
- 所在地
- 〒654-0081
兵庫県神戸市須磨区高倉台1-1-7
TerrasMaクリニックモール103
- 交通手段
-
山陽電鉄本線 月見山駅
JR神戸線(神戸~姫路)
須磨駅
山陽電鉄本線 山陽須磨駅駐車場 有/
患者さま専用駐車場あり